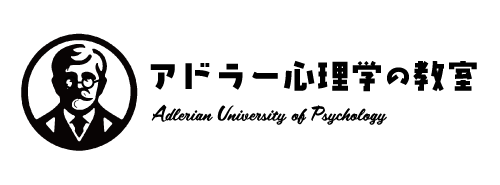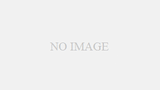はじめに(続き)
夜、子どもの寝顔を見つめながら「本当は仲良く話したかっただけなのに」と胸が締めつけられる。そんな夜を、何度迎えたことでしょう。
親だって、叱りたくて叱っているわけではない。ただ、大事なわが子だからこそ、つい強い言葉になってしまう。それなのに、思いがすれ違うたび、自分を責めたり、子どもとの間に距離を感じてしまったり…。
そんなふうに、親もまた、悩み、迷いながら育っていく存在です。
アドラー心理学は、親子を**上下ではなく“横の関係”**で見ることを提案します。
“上から教え導く存在”ではなく、“同じ人生の旅をしている仲間”として。
叱るかわりに信頼する。管理するかわりに任せる。比較するかわりに勇気づける。
――そんな、あたたかい親子関係の築き方を、ここから一緒に探っていきましょう。
1. 反抗・癇癪が止まらないとき
◇こんな気持ち、抱えていませんか?
「毎日毎日、どうして同じことを言わせるの…」
「怒りたくない。でも、どうしたらいいのかわからない」
叱ったあと、子どもがバタンとドアを閉めて部屋にこもる音――その音が、心にズシンと響く。
“わかってほしい”という思いが、伝わらないもどかしさ。
そんな苦しさ、きっとあなたも感じたことがあるはずです。
◇アドラー心理学での見立て(詳細に)
アドラー心理学では、子どもの反抗や癇癪も「ただ困った行動」とは捉えません。
それは子どもなりに、「私を見て」「私の気持ちをわかって」というメッセージなのです。
アドラーは、すべての行動には目的があるとする目的論を提唱しました。
反抗や怒りという形をとっていても、その根底には「所属したい」「認められたい」というごく自然な願いが隠れています。
また、子どもは未熟なために、気持ちをまっすぐ言葉にできず、”力”で伝えようとすることもあります。これをアドラーは誤った補償行動と呼びました。
つまり――
- 癇癪や反抗は、未熟な自己表現
- 本当は「信じてもらいたい」「理解されたい」と願っている
- しかし方法が未熟で、結果的に親との距離を広げてしまっている
このように捉えることで、表面的な「困った行動」ではなく、子どもの奥にある願いに目を向けることができるのです。
◇あたたかい解決アプローチ(詳細に)
【ステップ1】まず自分の心を落ち着かせる
怒りをぶつけると、子どもは「もっと強く出なければ」と感じ、反抗が悪化してしまいます。
そんなときは、まず親自身が3秒の深呼吸をして、自分の怒りを認めてあげてください。
「私は今、悲しくなっているんだな」「わかってほしかったんだな」と。
自分の感情に寄り添うことが、子どもへの寄り添いの第一歩になります。
【ステップ2】行動の裏にある気持ちを代弁する
ドアをバタン!と閉めた子に、こんなふうに声をかけてみましょう。
「ドアを強く閉めたね。きっと、言われたことがすごくイヤだったんだよね」
「やりたくない気持ち、教えてくれてありがとう」
子どもは「怒ったから叱られる」と身構えています。
でも親が**“気持ちをわかろう”**としてくれると、驚くほど早く心を開きます。
目的(=わかってほしい)が達成されるからです。
【ステップ3】課題の分離で責任を整理する
宿題や持ち物の準備など、基本的に子ども自身の課題は子どもに任せましょう。
「困ったら相談してね」とだけ伝え、手を出しすぎないことが大切です。
「あなたの冒険を応援しているよ」という態度を示すことで、子どもは自ら責任を引き受ける練習ができます。
【ステップ4】小さな挑戦を必ず認める
宿題が一問しかできなかったとしても、言葉にして伝えてください。
「始めたね。動き出すって勇気がいるよね」
結果ではなく、行動そのものを認める。
それが、子どもの「やってみよう」という心を育てる一番の栄養です。
2. 過干渉と放任の揺れ幅で疲弊するとき
◇こんな気持ち、抱えていませんか?
「ちゃんと見てあげないと…と思うけど、つい口うるさくなってしまう」
「もう疲れた、好きにして…と言った後で、夜中に後悔して眠れない」
心配するから、口を出してしまう。だけど、口を出すほど嫌われるような気がして、また不安になる。
――そんな、愛情ゆえの“やりすぎ”と“引きすぎ”のあいだで、心が疲弊してしまうこと、ありますよね。
◇アドラー心理学での見立て(詳細に)
アドラー心理学では、こうした親の苦しみも、「あなたが悪いから」ではないと見ます。
親が過干渉になったり、逆に放り出したくなったりする背景には、
- 「良い親でいたい」
- 「子どもを失敗させたくない」
という、切実な願いがあると考えます。
ただ、この願いが強すぎると、
「子どもの人生は自分がコントロールしなければ」という私的論理に偏りやすくなります。
アドラーは、人は本来自分の人生を自分で決める力(自己決定性)を持っていると考えました。
だから親の役割は、“成功させる”ことではなく、“子ども自身が選び、失敗から学べる土壌を整えること”なのです。
◇あたたかい解決アプローチ
【ステップ1】“見守る勇気”を自分に許可する
子どもが課題を抱えているとき、すぐに手を貸さず、まずはそっと見守る勇気を持ってみましょう。
うまくいかなかったとしても、「失敗できた」こと自体が、子どもの大きな学びになります。
見守ることは、放置することではありません。
「いつでも味方だよ」「困ったら一緒に考えようね」という安心感を、そっと伝えることです。
【ステップ2】家庭の中に“任せるルール”を作る
たとえばこんなふうに、家庭内ルールを決めてみましょう。
「宿題は自分でスケジュールを立てる」
「部屋の片づけは本人の自由。ただし困ったときはサポートを頼んでOK」
ルールを「押しつけ」ではなく、「家族の約束」として一緒に作ることが大切です。
ルール=子どもが自主性を発揮するための“枠組み”です。
【ステップ3】親自身が「完璧じゃない」ことを子どもに見せる
ときには親も、失敗したり、疲れたりしますよね。
そんなときこそ、正直にこう言ってみましょう。
「今日はママも疲れちゃった。ちょっとだけ休憩するね」
「パパも失敗したことあるんだ。そこから勉強してきたよ」
親が「失敗してもいい」「立ち直ってもいい」姿を見せることは、
子どもにとって何より大きな勇気づけになります。
3. 受験・進路をめぐる対立
◇こんな気持ち、抱えていませんか?
「いい学校に行って、将来困らないようにしてあげたいだけなのに…」
「でも子どもは、ぜんぜん親の気持ちをわかってくれない」
夜、願書の説明書きを読みながら、ふと手が止まり、
「私は本当に、子どものためを思っているのかな」と、
自分を問い返してしまう。そんな切ない夜もありますよね。
◇アドラー心理学での見立て(詳細に)
アドラー心理学では、こうした親子の対立も、悪いことだとは考えません。
なぜなら、親と子の間に違う目的があることは、当たり前だからです。
問題なのは、「どちらが正しいか」を争うパワー闘争に陥ることです。
親は「成功してほしい」と願い、
子どもは「自分で選びたい」と願う。
どちらも本気だからこそ、ぶつかる。
アドラーは、こう言いました。
「目的が違うとき、対話を止めてはいけない」
縦の支配をやめ、横に並んで、互いの願いを聴き合うこと。
それが、対立から信頼へ向かう第一歩になります。
◇あたたかい解決アプローチ
【ステップ1】親の願いと子どもの願い、どちらも“正直に書き出す”
まず、親の願い(例:安定してほしい、不安を減らしたい)と、
子どもの願い(例:好きなことを追いかけたい、自分で決めたい)を、紙に書き出してみましょう。
書き出すことで、感情ではなく情報として冷静に見つめられます。
【ステップ2】共通項を探して“小さな橋”をかける
書き出したリストの中から、「両方にとって大切なこと」を見つけます。
たとえば、
- 「自分で選んだ道を、最後まで責任を持つ」
- 「途中で困ったら相談できる」
など。
対立する点よりも、共通して守りたいものに意識を向けます。
【ステップ3】「あなたを信じている」と言葉にする
最後に、子どもに伝えてください。
「最終的にどうするかは、あなたが決めるんだよ」
「どんな道を選んでも、ママはあなたの味方だよ」
この言葉は、子どもにとって
「自分の人生を生きていいんだ」
という最大の勇気づけになります。
4. 兄弟間の比較で生まれる劣等感
◇こんな気持ち、抱えていませんか?
「この子にもちゃんと愛情を注いでいるはずなのに…」
「“どうせ私なんか”ってふさぎこむ姿を見ると、胸が痛い」
兄弟姉妹を育てていると、褒めたつもりの一言が、思わぬ棘になってしまうことがあります。
上の子を褒めたら、下の子がすっと目を伏せた。
励ましたつもりなのに、余計に自信をなくしてしまった。
――そのたびに、親もまた、自分を責めてしまいますよね。
◇アドラー心理学での見立て(詳細に)
アドラー心理学では、きょうだい間の劣等感についても、単に「やきもち」「甘え」だとは見ません。
そこには、
- 「自分もここにいていいと思いたい」
- 「大切にされたい、認められたい」
という、深く切実な願いがあると考えます。
アドラーが提唱した共同体感覚では、
「私はこの家族にとって大切な存在だ」と実感できることが、人の心の健やかさに直結するとされます。
しかし比較が日常化すると、
- 「できる・できない」
- 「勝った・負けた」
という、縦のものさしで自分を測るクセがついてしまいます。
劣等感は、子どもの自然な感情です。
でもそれを「劣っているからダメだ」と思わせないために、
親ができる工夫がたくさんあるのです。
◇あたたかい解決アプローチ
【ステップ1】“昨日の自分”との比較に切り替える
きょうだいを比べるかわりに、その子自身の成長を見つけましょう。
たとえば、
「昨日より10分長く勉強できたね!」
「先週はできなかった縄跳び、今日は5回跳べたんだ!」
昨日の自分と比べることで、小さな成長を自分自身で感じられるようになります。
「比べるなら、他人じゃなく、自分自身」という考え方を、少しずつ一緒に育てていきましょう。
【ステップ2】その子だけの“貢献感”をつくる
家族の中で、その子にしかできない役割をつくります。
たとえば、
- 妹は「お皿を並べる係」
- 弟は「玄関の靴をそろえる係」
など。
小さな役割でも、「助かったよ」「ありがとう」と声をかけることで、
自分は家族の大切な一員なんだという実感を育むことができます。
貢献感は、劣等感を乗り越える最大の力になります。
【ステップ3】“存在そのもの”を喜ぶ言葉を届ける
何かができたから、すごい。
何かに勝ったから、うれしい。
――ではなく、ただそこに「いてくれてありがとう」という言葉を、意識的に伝えていきましょう。
たとえば、
「あなたがここにいるだけで、家の中が明るくなるよ」
「今日も元気に帰ってきてくれて、ママはうれしいな」
できたことや結果ではなく、存在そのものを喜ばれる経験は、
子どもの心に深く、あたたかく、根を下ろしていきます。
まとめ
反抗、過干渉、受験対立、兄弟比較――
親子の悩みは、それぞれ違って見えて、
実はどれも、根っこにあるのは同じです。
それは、
「つながりたい」
「認められたい」
「信じてもらいたい」
という、ごく自然な、人間の願い。
アドラー心理学は、
- 子どもの行動の裏にある“目的”を見つめること
- 叱るより、勇気づけること
- 上下ではなく、横のパートナーとして関わること
を、そっと教えてくれます。
完璧な親になることを目指さなくていい。
完璧じゃないからこそ、親も子も、いっしょに育っていけるのだと、アドラーは教えてくれます。
次の記事「継親子」では、血のつながりを超えた親子関係において、
どんなふうに横の関係を築いていけるのかを、また一緒に考えていきましょう。