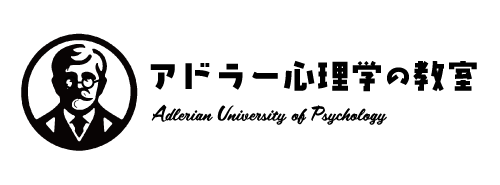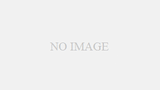はじめに
一緒に育ってきたからこそ、ぶつかることも多い。
気が合う日もあれば、まるで水と油の日もある。
兄弟姉妹の関係は、
親子とも、友だちとも違う、
特別な絆を持った存在です。
でも、
「どうしてこの子たちはこんなにケンカばかりするんだろう」
「上の子ばかり我慢させてしまっているかも」
――そんなふうに悩む親御さんも、きっと少なくありませんよね。
アドラー心理学は、
兄弟姉妹の関係にも、
優越感・劣等感・所属感という人間の根源的なテーマが関わっていることを教えてくれます。
ここでは、兄弟姉妹によく起こる3つの葛藤を取り上げながら、
アドラー流のあたたかい寄り添い方を一緒に考えていきましょう。
1. ケンカばかりで仲良くできないとき
◇こんな気持ち、抱えていませんか?
「せっかく兄弟がいるのに、毎日ケンカばかり」
「仲良くしてほしいだけなのに、なんでわかってくれないの」
仲良く遊ぶ日もあれば、
次の日には大げんか。
怒ってもなだめても、また繰り返す。
――そんな姿に、ため息が止まらなくなることもありますよね。
◇アドラー心理学での見立て
アドラー心理学では、兄弟げんかも、単なる問題行動ではなく、
「自分の存在を確かめたい」という行動だと捉えます。
特に小さい子どもにとって、兄弟姉妹は最初の社会です。
- 比べられる
- 認められたい
- 負けたくない
そんな思いが交錯するなかで、
試行錯誤しながら、どう関わればいいかを学んでいるのです。
つまり、ケンカもまた、
横の関係を練習している過程だといえるのです。
◇あたたかい解決アプローチ
【ステップ1】ケンカを“失敗ではなく学び”ととらえる
まず、「またケンカして!」と感情的に怒らず、
「今日はどんな気持ちがぶつかったのかな?」
と、お互いの気持ちに目を向ける対話にしてみましょう。
ケンカ=失敗ではなく、
関係を学ぶ貴重なレッスンだと受け止めることで、
子どもたちは「自分の気持ちを表現していいんだ」と安心できるようになります。
【ステップ2】問題解決をサポートしながら任せる
どちらが悪い、正しい、を決めるのではなく、
「どうしたら二人が納得できる方法になるかな?」
と問いかけてみましょう。
親が審判にならず、対話のファシリテーターになることで、
子どもたち自身が問題解決能力を育てていきます。
【ステップ3】“どちらも大事”を行動で伝える
一方をかばったり、もう一方を責めたりせず、
たとえば、両方の名前を呼んで、
「〇〇も△△も、大事な大事な家族だよ」
と伝えましょう。
愛情は競争しなくても手に入ると感じることが、
兄弟姉妹の横のつながりを育てる土台になります。
2. 上の子にばかり我慢させてしまうとき
◇こんな気持ち、抱えていませんか?
「上の子には、どうしても“お兄ちゃんだから”って求めてしまう」
「気づけば、我慢させてばかりで、申し訳なくなる」
小さいきょうだいに手がかかる分、
つい上の子に期待してしまう。
そんなふうに、自分を責めてしまう夜もありますよね。
◇アドラー心理学での見立て
アドラー心理学では、兄弟姉妹の間にも、優越感と劣等感の影響を見ます。
上の子は、
- 「頼られることで価値を感じる」
- 反面、「甘えたいのに甘えられない」
という葛藤を抱えがちです。
アドラーは、人が心から勇気を持てるのは、
無条件に存在を受け入れられたときだと考えました。
だからこそ、
「お兄ちゃんだからできるよね」ではなく、
「あなた自身がかけがえのない存在だよ」と伝えることが大切なのです。
◇あたたかい解決アプローチ
【ステップ1】年齢や立場ではなく、その子自身を見つめる
上の子が何か我慢している様子に気づいたら、
「本当はどうしたかった?」
と、そっと聞いてみてください。
立場ではなく、一人の人間として気持ちを尊重することが、
心の勇気を支えます。
【ステップ2】「ありがとう」よりも「一緒に」でつながる
上の子にお手伝いをお願いするときも、
「一緒にやろうか」
と声をかけてみましょう。
任せるのではなく、支え合う仲間として関わることで、
上の子も「頑張らされている」のではなく、
「信頼されている」と感じられるようになります。
【ステップ3】上の子だけと過ごす特別な時間をつくる
ほんの10分でもいいので、
上の子だけと向き合う時間を持ってみましょう。
- 本を読む
- 近くを散歩する
- 好きな話を聞く
「あなたも甘えていいんだよ」というメッセージを、
行動で届けてあげましょう。
3. きょうだいで性格がまったく違うとき
◇こんな気持ち、抱えていませんか?
「同じように育ててきたのに、どうしてこんなに違うんだろう」
「どちらも大切なはずなのに、接し方がわからなくなる」
上の子はコツコツ型、下の子は自由奔放。
兄は人懐っこいけれど、弟は警戒心が強い。
――そんなふうに、きょうだいで性格がまったく違うと、
親としてもどう向き合えばいいのか、悩んでしまうことがありますよね。
◇アドラー心理学での見立て
アドラー心理学では、
同じ家庭環境に育っていても、
子ども一人ひとりが自分だけの**私的論理(ものの見方・捉え方)**を形成すると考えます。
つまり、
- 同じ出来事を経験しても、受け止め方はそれぞれ違う。
- 性格は環境だけで決まるのではなく、子ども自身が「どう生きるか」を主体的に選び取っている。
アドラーは、
「人は環境に反応する存在ではない。環境に対する態度を自ら決める存在だ」
と言いました。
だからこそ、きょうだいが違うのは自然なことであり、
親がそれぞれの“違い”を認め、尊重することが大切なのです。
◇あたたかい解決アプローチ
【ステップ1】「違い=価値」と考え方を切り替える
きょうだいの性格の違いを、
「どちらが正しいか」
「どちらが育てやすいか」
で測らないように意識してみましょう。
それぞれの個性を、
「あなたにはあなたの素晴らしさがあるね」
と言葉にして伝える。
違いを“個性”として尊重された子どもは、
他者とも自分とも、より豊かな関係を築いていけます。
【ステップ2】比較ではなく、個別の目標と応援を
たとえば、コツコツ型の子には「計画を立てる力を育てる」応援を、
自由奔放型の子には「発想を広げる力を活かす」応援を。
子どもたち一人ひとりに合わせて、
「君の強みを応援するよ」
というスタンスで寄り添っていきましょう。
【ステップ3】きょうだい同士の“助け合い”を促す
性格が違うからこそ、補い合える場面も生まれます。
たとえば、
- 落ち着きのない弟の遊びを、慎重な兄がフォローする。
- こだわりの強い姉に、柔軟な弟が新しいアイデアを出す。
親が「二人が一緒だと強いね」とフィードバックすることで、
違いを活かし合う横の関係が育っていきます。
まとめ
兄弟姉妹の関係は、
時にライバルであり、時に最高の仲間であり、
人生で最も長く続く「練習試合」のような存在です。
アドラー心理学は、
- ケンカも、
- 我慢も、
- 性格の違いも、
すべてが、人と人とが支え合って生きるための練習だと教えてくれます。
親ができることは、
- 競争ではなく協力を促し、
- 比較ではなく個性を讃え、
- 失敗ではなく成長を信じること。
そしてなにより、
「あなたたち一人ひとりが、大切な存在だよ」
と、繰り返し、繰り返し、伝え続けることです。
きょうだい同士も、
親と子も、
みんな、いっしょに少しずつ育っていく――
それが家族という、小さな共同体なのかもしれませんね。