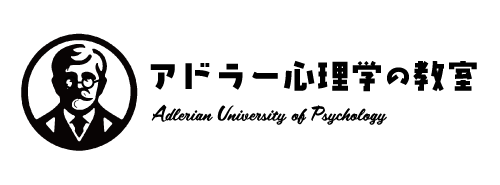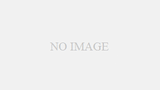はじめに
「この子の親になりたい」と心から願い、
「この子の未来を一緒に育てたい」と覚悟を決めた――。
養子縁組は、奇跡のような出会いの物語です。
けれど、愛だけでは埋めきれない不安に、そっと胸を押さえる日もあるかもしれません。
「本当に私を家族だと思ってくれているかな」
「生みの親に申し訳ないと、思わせてしまわないだろうか」
そんなふうに、相手を思う優しさゆえに、
自分自身を縛ってしまうこともあるでしょう。
アドラー心理学は、どんな人間関係も、
血縁ではなく、信頼と貢献を通じて育まれるものだと教えます。
ここでは、養親子の間に起こりやすい3つの葛藤をもとに、
アドラー流の温かい視点と、具体的な寄り添い方を一緒に探っていきます。
1. 「本当に親と思ってくれるのかな」と不安になるとき
◇こんな気持ち、抱えていませんか?
「この子の“お父さん・お母さん”になりたい。でも本当にそう呼んでくれるだろうか」
「無理に愛されようとしていないかな、と不安になる」
子どもにとって大切な存在になりたいと願うほど、
「ちゃんと親になれているだろうか」という不安が押し寄せる。
そんな、見えない寂しさに、ひとり立ち向かっているあなた。
――本当に、よく頑張っていますね。
◇アドラー心理学での見立て
アドラー心理学では、親子関係もふくめ、信頼は命令できないと考えます。
信頼は、「この人なら安心できる」という子どもの内側から湧きあがるもの。
- 愛していること
- 支えになりたいこと
これらを、言葉や態度で少しずつ伝え続けるなかで、
子ども自身が、自分のペースで“この人を信じてみようかな”と思えるようになっていくのです。
焦らず、信頼の芽を待つこと。
それこそが、養親子関係における、なにより尊い姿勢です。
◇あたたかい解決アプローチ
【ステップ1】「親になろう」とするより、「ただここにいる」
子どもに何かを証明しようとしなくていいのです。
ただ、失敗しても、怒られても、悲しいときも、
あなたが変わらずそこにいること。
それが、子どもにとって何よりの安心になります。
【ステップ2】子どもの選択を尊重する
子どもが呼び方をどうするか、どこまで心を開くか。
それはすべて、子どものペースに任せて大丈夫です。
「どう呼んでも、どう思っても、あなたの自由だよ」
と伝えることで、子どもは“選ぶ自由”を手にし、
安心してあなたに近づくことができるようになります。
【ステップ3】小さな日常を丁寧に積み重ねる
特別なイベントよりも、毎日の「おはよう」「おやすみ」「いただきます」。
このさりげない積み重ねが、
やがて「この人は、どんなときも自分のそばにいてくれる」という確信につながっていきます。
2. 生みの親への思いを、どう受け止めたらいいかわからないとき
◇こんな気持ち、抱えていませんか?
「生みの親のことを想う気持ちを、否定したくない」
「でも、私の存在が“代わり”だと思われたら、悲しい」
子どもが過去を大切に想うことを、
喜んであげたい。
でも、そのたびに小さく痛む自分の心に気づいてしまう。
――その葛藤は、とても人間らしく、尊いものです。
◇アドラー心理学での見立て
アドラー心理学では、「過去は変えられない。しかし、過去に与える意味は変えられる」と考えます。
子どもにとって、生みの親は、たとえどんな事情があったとしても、
かけがえのない存在です。
そして、あなたもまた、今を一緒に生きる、かけがえのない存在です。
どちらか一方を否定する必要はありません。
過去を大切にしながら、今も大切にする。
それが、子どもにとって一番の支えになります。
◇あたたかい解決アプローチ
【ステップ1】生みの親の存在を尊重する
子どもが生みの親について話したとき、
静かに、こう伝えてみてください。
「あなたにとって大事な人なんだね」
否定も肯定もせず、ただ受け止めること。
それだけで、子どもは「ここでも過去を大切にしていいんだ」と安心できます。
【ステップ2】子どもの気持ちに寄り添いながら、自分の気持ちも大事にする
悲しみや痛みを感じたときは、
「私も、あなたと出会えたことを心からうれしく思っているよ」
と、自分の素直な気持ちも、そっと伝えてください。
子どもは、大人の本音に触れることで、
“ここは安心できる場所だ”と感じられるようになります。
【ステップ3】「二つの愛」が共存できることを、教えてあげる
「人の心は、いくつもの大切なものを同時に持てるんだよ」
子どもにとって、過去を大切にすることも、
今を大切にすることも、
どちらも間違いではありません。
それを言葉で教えてあげるだけで、
子どもはきっと、自分を許し、愛する力を育てていきます。
3. 自立とともに距離が生まれるとき
◇こんな気持ち、抱えていませんか?
「小さかったころは、もっと無邪気に甘えてくれたのに」
「最近は、あまり話してくれない」
子どもが自立に向かって歩き出すとき、
それは喜ばしいことだとわかっていても、
どこか胸の奥がすうっと寂しくなること、ありますよね。
特に養親子の場合、
「やっと築けた信頼が離れていってしまうんじゃないか」
そんな、少し特別な不安も、そっと心に忍び込むかもしれません。
でも、それは、関係が壊れるサインではありません。
むしろ、信頼してもらえたからこそ、自立できる。
それがアドラー心理学が教える、親子の自然な成長プロセスです。
◇アドラー心理学での見立て
アドラー心理学では、
人間の成長とは「自己決定性を強めていくこと」だと考えます。
つまり、
- 子どもが自分で考え、
- 自分で選び、
- 自分で責任を持つようになること。
それは親に対する拒絶ではなく、
あなたを信頼しているからこそ、自分の足で歩こうとしている証拠なのです。
親が子どもの自立を祝福し、
必要なときにだけそっと支える。
このバランスこそ、横の関係の成熟した形だとアドラーは考えました。
◇あたたかい解決アプローチ
【ステップ1】「離れること=愛が消えることではない」と信じる
子どもがそっけなくなったり、
自分の世界に閉じこもる時間が増えたりしても、
それは「愛がなくなった」わけではありません。
子どもは、“親に依存しなくても大丈夫だと信じられるようになった”から、
世界を広げているのです。
そのたびに、心の中でそっとつぶやいてください。
「この子は、ちゃんと育っている」
【ステップ2】必要なときに“応援団”として現れる
干渉はせず、でも困ったときには必ず力になれるように、
見守る場所からそっと応援していましょう。
子どもが助けを求めたときは、すぐ手を差し伸べてOK。
でも、それまでは“信じて任せる”。
この姿勢が、
「いつでも戻れる場所がある」という安心を育てます。
【ステップ3】自分自身の人生も大切にする
子どもが自立に向かうなら、
あなたもまた、自分の人生を豊かにする時間です。
趣味を広げる。
友人と出かける。
新しいことに挑戦する。
あなたがあなた自身を大切にする姿は、
子どもにとって、最高の手本になります。
そして何より、あなた自身の幸せが、
家族全体の幸福感を底上げしていくのです。
まとめ
養親子の絆は、血のつながりだけでは語れない、
深い、あたたかな信頼の物語です。
子どもが生まれてきた背景も、
出会ったときの状況も、
すべて含めて、今、ここに一緒にいる。
その奇跡を、
アドラー心理学はそっと後押ししてくれます。
- 無理に親らしく振る舞わなくてもいい
- 過去を否定せず、今を大事にすればいい
- 離れていく子どもを、信じて見送ればいい
焦らず、比べず、
一歩ずつ、一緒に育っていきましょう。
あなたのそのまっすぐな愛情は、
きっと、ちゃんと伝わっています。
次回は「兄弟姉妹」のテーマに進み、
同じ家庭のなかで育つ子どもたちの関係を、
アドラー心理学から見つめていきますね。