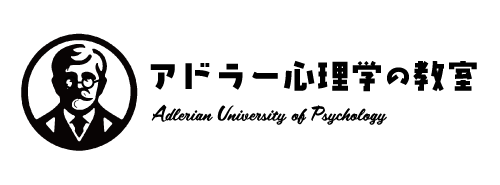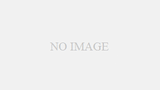はじめに
- 研究テーマを探りながら
- 論文執筆に取り組みながら
- 専門性を高めながら
指導教員と大学院生の関係は、
単なる「教える・教わる」だけではない、
**「ともに学び、支え合うパートナーシップ」**です。
しかし現実には、
- 指導が厳しすぎて苦しくなったり
- 意見が食い違って対立したり
- 適切な距離感がわからなくなったり
そんな難しさを感じる場面も少なくありません。
アドラー心理学は、
どんな関係性でも
**「対等な横の関係」と「勇気づけ」**が大切だと教えています。
ここでは、指導教員と大学院生の関係でよく起こる3つの葛藤をもとに、
アドラー流のあたたかい寄り添い方を一緒に考えていきましょう。
1. 指導が厳しすぎて関係がぎくしゃくするとき
◇こんな気持ち、抱えていませんか?
教員:「厳しく指導しないと育たないのでは…」
院生:「ダメ出しばかりで自信がなくなる…」
- 真剣だからこそ
- 成長を願うからこそ
厳しく接してしまうこともあるけれど、
それが心をすり減らしてしまうこともありますよね。
◇アドラー心理学での見立て
アドラー心理学では、
**「厳しさより勇気づけ」**を重視します。
- ミスを責めるのではなく
- 努力や成長に目を向ける
それが、真に自立した研究者を育てる道です。
◇あたたかい解決アプローチ
【ステップ1】「できている部分」を意識して伝える
- 批判だけでなく
- 小さな進歩にも目を向け
「ここは良くなったね」と具体的にフィードバックしましょう。
【ステップ2】「今後に活かす視点」で指導する
過去を責めるのではなく、
「次はどうすればもっとよくなるか」
に焦点を当てた指導を心がけましょう。
【ステップ3】指導する側も「完璧」であろうとしない
教員も間違うし、学び続ける存在。
その自然体な姿勢が、院生の安心感につながります。
2. 意見が食い違ったときに関係が悪くなるとき
◇こんな気持ち、抱えていませんか?
教員:「この方向性で進めた方がいいと思うけど、納得していないようだ」
院生:「自分の考えを否定された気がして苦しい」
- 研究の進め方
- 仮説の立て方
- 方法論の選択
意見がぶつかることは、
成長のための大事な過程です。
けれど、うまく対話できないと、
信頼関係にひびが入ることもありますよね。
◇アドラー心理学での見立て
アドラー心理学では、
**「支配ではなく対話」**を重視します。
- 上から押し付けるのではなく
- 対等に話し合う
そんな関わりが、創造的な関係を育てるのです。
◇あたたかい解決アプローチ
【ステップ1】「なぜそう考えたか」を互いに聞き合う
意見の表面だけでなく、
背景や動機を理解し合いましょう。
【ステップ2】「正しさ」を競わない
どちらが正しいかを争うのではなく、
「より良い道を一緒に探す」
というスタンスを持ちましょう。
【ステップ3】違いを「学び」として受け取る
考えが違うことは、
お互いの成長のチャンスです。
違いを歓迎する心を育てましょう。
3. 距離感に悩むとき
◇こんな気持ち、抱えていませんか?
教員:「どこまで手を出していいのか、放っておくべきなのか迷う」
院生:「もっと相談したいけど、迷惑かも…」
- 指導の入り方
- 支援の手加減
- 自立への距離感
適切なバランスを取るのは、意外と難しいものです。
◇アドラー心理学での見立て
アドラー心理学では、
**「自立支援型の関わり方」**を理想とします。
- 手を貸しすぎず
- 放置もせず
- 自立を促すための支えとなる
そんな関わり方が、互いの成長を後押しします。
◇あたたかい解決アプローチ
【ステップ1】「困ったらいつでも相談していい」と伝える
依存させるのではなく、
サポートの扉を開いておくことが安心感につながります。
【ステップ2】小さな成功を一緒に喜ぶ
- 修論の小さな進展
- 小さな発表での成長
小さな成功を共に喜ぶことで、自立への自信が育ちます。
【ステップ3】時には「信じて任せる」
手出しせず、
「あなたならできる」
と信じて見守る勇気も大切です。
まとめ
指導教員と大学院生の関係は、
- 支え合いながら
- 学び合いながら
- ともに成長していくパートナーシップです。
アドラー心理学は教えてくれます。
- 上下ではなく対等な関係で
- 勇気づけ合いながら
- 互いの成長を支援すること
それが、
本当に健やかで豊かな教育関係を育てる道だと。
今日、
- 小さな「よく頑張ったね」
- 小さな「一緒に考えよう」
そんなひと声が、
未来の研究者を育てる温かい支えになります。