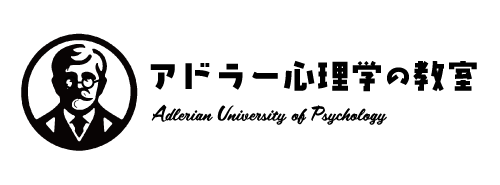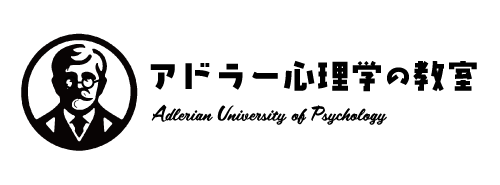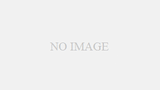1. はじめに
アドラー心理学を理解するうえで欠かせない概念のひとつが「目的論」です。一般的には、人間の行動や感情を「過去の原因」によって説明しようとする流れが強いなか、アドラーは真逆ともいえる「未来の目的」に注目しました。これはフロイトが主張した「原因論的アプローチ」との対比でも語られることが多く、アドラー心理学を特徴づける大きな要因となっています。
本記事では、まず目的論の概要を整理したうえで、原因論との違いや、目的論を日常生活でどのように活かせるのかについて詳しく解説します。アドラーがなぜ「人は目的に向かって生きる」という視点を大切にしたのか、その理由を知ることで、アドラー心理学の本質がより深く理解できるでしょう。
2. アドラー心理学における目的論の位置づけ
2-1. 「過去」ではなく「未来」に目を向ける
アドラー心理学の基本姿勢として、「人間の行動や感情は、その人が目指しているゴール(目的)によって決まる」という考え方があります。例えば、ある人が日常的に「自分はダメだ」と感じて落ち込んでいるとしましょう。原因論的にみれば、「幼少期に親から厳しい言葉をかけられた」「学校での失敗体験がトラウマになった」など、過去の出来事を手がかりに考えがちです。もちろんこれらの要因が影響を与えることを否定するわけではありません。しかし、アドラーの立場では、**「では、なぜその人は『自分はダメだ』と感じ続けることを、今、選んでいるのか?」**という問いが重視されます。
「自分はダメだ」と感じ続ける背景には、「失敗を避けるために行動しない口実をつくっている」「人から同情やサポートを得やすくするために自己卑下の態度を取っている」などの“目的”が隠れているかもしれません。これは当人の意識レベルで自覚しているとは限らず、あくまで深層心理的な狙いかもしれませんが、アドラー心理学では、こうした未来に向けた意図や方針にフォーカスします。
2-2. 全体論・自己決定性との関連
アドラーの目的論は、「人間は部分に分割できない統合された存在であり(全体論)」「自らの行動を主体的に決定している(自己決定性)」という他の原則とも密接に結びついています。人間が自らの人生を切り開くうえで、過去の影響だけではなく、**「これから何を目指しているのか?」**が大きなモチベーションとなるからです。
3. 目的論と原因論の違い
3-1. フロイトとの比較
アドラーが活躍した時代、心理学の主流はフロイトの精神分析でした。フロイトはトラウマや幼児期の体験が人間の無意識や人格形成に大きく影響すると考え、「幼少期の体験がその人の現在の行動や思考様式をつくりあげる」という原因論的な姿勢をとりました。
一方でアドラーは「同じようなトラウマをもつ人であっても、その受け止め方や行動の仕方は人それぞれ異なる。過去そのものが直接、現在を決定するわけではない」と主張し、「いまその人が向かっている目的」に着目しました。つまり、**「過去の出来事は、その人が何らかの目的を選択・追求する際の材料にすぎない」**と考えたのです。
3-2. 原因論では説明しきれない個人差
原因論だけでは、同じ経験をした人がまったく違う行動様式や人生の捉え方をする理由を十分に説明しきれません。例えば、幼少期に厳格な父親から虐待的な扱いを受けたとしても、それをバネにして「自分は絶対に同じことをしない、子どもには愛情深く接しよう」と決意する人もいれば、「自分は愛されなかったから、他者を傷つけてもかまわない」と諦めに近い態度で生きる人もいるでしょう。
アドラーによれば、この違いを生むのが「目的」であり、私たちはどんな過去をも材料として、未来志向で解釈し直し、自分なりのライフスタイルを築いているというわけです。
4. アドラー心理学以外の学説との比較
4-1. 行動主義との違い
行動主義心理学は、観察可能な「刺激と反応」の関係に着目します。人の行動は、環境から与えられる刺激や報酬・罰などによって形成されると捉えるので、原因論的な色彩が強い傾向にあります。アドラーの目的論は、外部要因だけでなく、個人の内面的なゴール設定を重視するため、行動主義とは根本的に立脚点が異なると言えるでしょう。
4-2. 来談者中心療法(ロジャーズ)との親和性
一方、カール・ロジャーズの来談者中心療法は、「人間には自己実現に向かう傾向(自己実現傾向)がある」として、クライアントの主体性を重んじる考え方です。これはアドラーの「目的を見据えて自己を変革する力が人間にはある」という主張とも親和性が高い部分です。ただ、ロジャーズは過去・未来という時間軸よりも、**「いまここでの自己体験」**に重点をおくので、厳密にはアドラーの目的論とはやや立ち位置が異なるともいえます。
5. 目的論がもたらす実践的メリット
5-1. 過去に縛られない生き方
目的論を日常生活で活かす最大のメリットは、「自分の人生を過去から解放する」という点でしょう。もちろん、誰しも幼少期の体験やトラウマに影響を受けますが、**それが「今の自分の生き方を制限する決定要因ではない」**と考えられるようになることで、前向きな変化の余地を見出せます。
例えば、「親が自分を認めてくれなかったから、自分には価値がない」と思い込んでいる人は、目的論の視点に立てば、**「では、なぜ自分は『親に認められなかった』という記憶を、今もなお『価値がない』というセルフイメージにつなげ続けるのか?」**と考えられます。その裏側には「自己評価を低く保つことで、挑戦を避ける」という目的が隠れているかもしれません。そこに気づければ、新たな目標を設定し、行動を変えていくきっかけになります。
5-2. 自分自身を主体的に捉えられる
原因論的な捉え方では、人は過去や環境の被害者であるかのように感じやすく、「自分の人生は決まってしまったもの」という無力感を生みがちです。これに対し目的論は、「私たちは過去の出来事を材料としながらも、未来に向かって自らゴールを選び、そのゴールに合わせた行動をしている」という主体的な捉え方を促します。
結果として、「自分は選択する力を持っている」という自尊感情を高めることにつながりやすいのです。これは自己決定性を重視するアドラー心理学全体の思想とも密接にリンクします。
5-3. 対人関係を円滑にする
目的論を理解すると、自分だけでなく他者に対しても「この人はどんな目的をもって、いまの行動をしているのだろう?」と考える視点を持つようになります。例えば、職場で上司にいつも怒り口調で指示をされて困っている場合、ただ「怒りっぽい人だ」と原因論で片づけるのではなく、「もしかすると『自分の権威を保ちたい』とか『プロジェクトの失敗を避けたい』など、何らかの目的があって、その手段として怒りを選んでいるのかもしれない」と推測してみることができます。
こうした推測は、相手の感情や行動を客観的に理解し、コミュニケーションの糸口を探るうえで有効です。結果として対人関係が改善する可能性が高まります。
6. 目的論を日常生活で活かす方法
6-1. 自分の「隠れた目的」を探る質問
- 「いま自分が感じている感情やとっている行動には、どんな狙いがあるだろうか?」
- 「この感情や行動を続けて得られるメリットや回避できるデメリットは何だろう?」
こうした自己探求の問いを立てることで、原因論的な「過去のせい」にとどまらず、自分が無意識に設定している目的に気づきやすくなります。
6-2. 目的を再設定する
もし「自分を守るために無意識に目指している目的」が、結果として自分の成長や幸福を阻害していると気づいたら、新たな目的を設定することを試みます。例えば、「失敗を避けるために自己卑下する」という目的を、「より大きな挑戦をすることで達成感や他者への貢献を得る」という目的に書き換えてみるのです。
ここで重要なのは、「書き換え」そのものは行動を変える第一歩であって、一瞬で劇的に変化するとは限らないということです。それでも、新しい目的を意識的に持つことで、日々の小さな選択が変わり、長期的には大きな変化につながっていきます。
6-3. 他者への理解に活かす
先述したように、相手の行動を「目的論的にみる」視点を持つと、コミュニケーションのトラブルが減りやすくなります。「なんでそんなことするの?」とイライラする場面でも、**「もしかしたらこういう目的があるのかな?」**と仮説を立てられるからです。
もちろん、相手の本当の目的を勝手に決めつけるのは危険です。ただ、「目的があるかもしれない」という可能性を視野に入れるだけでも、対人関係に余裕が生まれます。最終的には、相手の言葉に耳を傾けながら「お互いの目的」をすり合わせることが、建設的な関係づくりに役立つでしょう。
7. まとめ
アドラー心理学における目的論は、**「人は未来に向かって生きる」「行動や感情には何らかの目的がある」**という視点を強調し、過去の原因に縛られがちな考え方とは一線を画します。これにより、私たちは自分の現在の状況や行動を、「どうしてそうなっているのか」だけでなく「どこへ行こうとしているのか」という観点からとらえ直すことが可能になります。
- 目的論を取り入れるメリット
- 過去に振り回されない: 自分の中に主体的に目的を設定する余地がある。
- 自己理解が深まる: 「自分は何を達成しようとしているのか?」という内省の問いを得られる。
- 対人関係を円滑にする: 他者の行動にも隠れた目的があると考えることで、余裕をもって対処できる。
アドラーが意図したのは、決して「過去をまったく無視すること」ではなく、「私たちは何を目指してそれをどう活かすのか」に目を向けることです。自分や相手の中にある目的を健全に見つめ直し、必要とあれば軌道修正する――そのプロセスこそが、アドラー心理学の目的論が示す自己変革の可能性なのです。