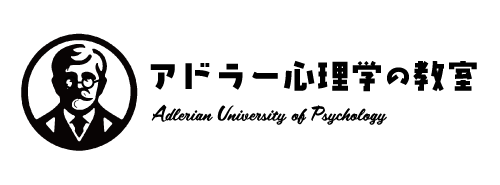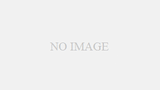1. はじめに
アドラー心理学では、「人間は環境や過去に決定されるのではなく、自らの意思によって選択し、行動している」という**自己決定性(Self-determination)**が強く主張されます。これは、原因論的な視点とは大きく異なるアドラーの特徴的な考え方の一つであり、「目的論」「認知論」とともにアドラー心理学を支える重要な柱となっています。
本記事では、自己決定性の具体的な意味や、なぜアドラーがこれを重視したのかを深堀りします。加えて、自己決定性を阻害する原因や、それを日常生活でどのように活かせるのか、具体的なヒントをご紹介します。
2. 自己決定性とは何か
2-1. 「自分の人生は自分で決める」という基本姿勢
自己決定性とは、簡単に言えば**「自分の行動や感情は自らが選んでいる」**という考え方です。たとえば、「あの人のせいでイライラする」という表現はよく耳にしますが、アドラー的には、「イライラすることを自分で“選択”している」と見るのです。もちろん、外的な刺激や状況が影響しないわけではありませんが、最終的には「どう感じ、どう行動するか」は本人の意思決定にかかっているというわけです。
2-2. 過去や環境をどう活かすかは自分次第
アドラーは過去のトラウマや育った環境が無意味だとは言いません。ただし、**「同じような体験をした人でも、その後の人生が大きく異なるのはなぜか?」**という問いに対して、アドラーは「本人がどう解釈し、どう活かすかを決めているから」と考えます。つまり、過去は単なる材料であって、そこから未来を作るのは現在の自分の選択次第だということです。
3. アドラー心理学における創造的自己(Creative Self)
3-1. 人は自分を“創造”している
アドラーは自己決定性をさらに進めて、「人間は自分自身を“創造的自己”として絶えず創り上げている」と述べています。これは、単に受動的に環境に反応して行動を決めるのではなく、自分の人生の主体となって、能動的に自分を作り変えていく力があるという主張です。
たとえば、困難な状況に置かれたとき、「もうダメだ」と諦めるのも選択、「何とか打開しよう」と試みるのも選択です。どちらの選択をするかによって、その後の人生の展開は大きく変わります。アドラーは、この選択の主体が「創造的自己」であり、私たちは無意識・意識レベルの両面で絶えず自己を再定義し続けていると考えました。
3-2. ライフスタイルとの関係
アドラーのもう一つの重要概念である「ライフスタイル」は、幼少期に形成された信念体系や行動パターンを指します。ライフスタイルは一見、固定されたもののように思えますが、実際には「創造的自己」がそれを取捨選択し、修正し続ける余地があるとも言えます。
- 決まったライフスタイルに従うのか?
- それを変革する(創造する)のか?
ここにも自己決定性が働く余地があるわけです。
4. 自己決定性がもたらす意義
4-1. 被害者意識からの解放
自己決定性を理解すると、「自分は被害者である」という意識から解放されやすくなります。「あの人のせいで私は不幸だ」「こういう家庭に生まれたから、こうなるしかない」という考え方は、ある種の無力感を伴います。しかしアドラーは、**「その解釈を選び、今そのように感じているのは自分だ」**という視点を与えます。これにより、過去や周囲の環境に支配されず、少しずつ自分の行動や思考パターンを変えていくモチベーションが生まれるのです。
4-2. 変化への勇気が湧いてくる
自分の行動や感情が自己決定によって生まれていると知れば、逆に言えば「変えることもできる」という希望につながります。過去や遺伝、性格などを絶対視して「どうにもならない」と思うのではなく、**「自分の捉え方次第で、人生を変える選択をとれるかもしれない」**という前向きな姿勢にシフトできるのです。これはアドラー心理学のキーワードである「勇気づけ(Encouragement)」にも深く関連します。
5. 自己決定性を妨げる要因と対策
5-1. 劣等感や恐れ
多くの場合、自己決定性を発揮できない背景には「劣等感」や「失敗への恐れ」があります。たとえば、何か新しいチャレンジをしたいと思っても、「自分には無理だろう」「恥をかきたくない」といった不安が先立ち、最初の一歩を踏み出せないことがあるでしょう。アドラーは、こうした劣等感そのものは必ずしも悪いものではなく、克服のための原動力にもなり得ると考えています。つまり、「恐れを持ちながらも行動を選択できる」ことこそが、自己決定性の発揮につながるというわけです。
5-2. 環境や周囲の圧力
職場の人間関係や社会的プレッシャーなど、外部からの圧力が大きいと感じる状況では、「自分にはどうしようもない」と思いやすくなります。しかし、アドラーの立場では、たとえ外部要因が大きくとも、その中で「どんな態度を取るか」「どう行動を変えていくか」はやはり個人の選択余地だと考えます。たとえば、「しんどい職場だから何もできない」と嘆くのではなく、**「何ができるか」**に焦点を当てて少しずつ行動を起こしていく姿勢が重要です。
5-3. 「相手の領域」との混同
自己決定性を阻害するもうひとつの要因として、**「他者の課題に介入しすぎる(または他者が自分の課題に介入してくる)」**ことが挙げられます。アドラー心理学でいう「課題の分離」は、まさに自己決定性と密接に絡んだ考え方です。他人の評価や行動を完全にコントロールすることはできません。したがって、自分の領域(自分がコントロールできる範囲)に集中し、そこにおける選択や責任を引き受けることが、自己決定性を高めるポイントになります。
6. 日常生活での実践方法
6-1. 「〜せざるを得ない」を「〜を選ぶ」に言い換える
よく使ってしまうフレーズに「〜しなければならない」「〜せざるを得ない」があります。これを意識的に「〜したい」「〜を選ぶ」と言い換えてみると、自分の意識に大きな変化が起きます。たとえば、「仕事だから朝早く起きなければいけない」を「自分が仕事をすることを選んでいるから、早起きを選んでいる」という表現に変えるだけで、自分の行動に対する主体性が見えてくるでしょう。
6-2. 小さな決断から始める
自己決定性を高めるために、いきなり大きな人生の選択を迫られる必要はありません。日常の些細な場面でも、**「今、私は何を選んでいるのか?」**を意識するだけで十分です。たとえば、ランチのメニューを選ぶときに「これしかないから仕方なく」という思考ではなく、「今日はあえてこのメニューを選ぼう」という意識を持ってみる。こうした小さな積み重ねが、自分の人生を主体的に生きる感覚を育んでいきます。
6-3. 自己対話の時間を設ける
忙しい日々の中では、自分の思考や選択をじっくり振り返る時間を持つのが難しいかもしれません。しかし、少なくとも1日に数分でも、「今日、自分が下した選択はどんなものだったか?」「そこにはどんな目的や意図があったのか?」と内省する習慣をつくると、自己決定性に対する意識が高まります。日記を書いたり、瞑想を取り入れたりと、自分に合った方法で自己対話を実践するとよいでしょう。
7. まとめ
アドラー心理学における自己決定性(Self-determination)は、**「人は過去や環境に支配される存在ではなく、現在・未来に向けて自らの行動や感情を選択できる」**という力強いメッセージを含んでいます。これを実践に移すことで、以下のような恩恵が得られます:
- 被害者意識からの脱却: 「自分にはどうにもできない」という無力感を手放すきっかけとなる。
- 変化する勇気: 過去や性格に縛られず、新たな行動を試みるモチベーションが高まる。
- 課題の分離と尊重: 自分がコントロールできる範囲に集中し、他者の領域を尊重することで、対人関係が円滑になる。
自己決定性を認めることは、ときに「責任を背負う」というプレッシャーも伴います。しかし、その責任を引き受けるからこそ、人は自分の人生に主体的に関わり、より満足度の高い生き方を実現できるのです。アドラーが説くように、私たち一人ひとりには「今ここ」から自分を創り上げていく力が備わっている――そのことに気づくことこそが、アドラー心理学の大きな恩恵と言えるでしょう。