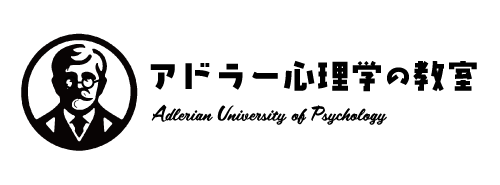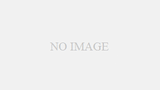1. はじめに
アドラー心理学では、「人間のあらゆる悩みは対人関係のなかで生まれる」とされます。そこから導かれるキーワードが「共同体感覚 (Community Feeling)」です。共同体感覚とは、「自分が属する社会や周囲の人々とのつながりを実感し、そこに貢献できているという感覚」を意味します。アドラーはこの感覚を得ることこそが、人間が幸福や充実を感じるために不可欠だと考えました。
近年、日本においては著書『嫌われる勇気』などを通じて、「共同体感覚=自己受容・他者信頼・貢献感」と表現されることが多くなりました。本記事では、共同体感覚の具体的な意味や欠如した場合の影響、そしてどのように育んでいくかについて、詳しく解説していきます。
2. 共同体感覚とは何か
2-1. アドラーの社会的存在論
アドラーによれば、人間はもともと「社会的存在」であり、完全に孤立して生きることはできないとされます。私たちが所属する家族、学校、職場、地域社会、さらには国や世界といったコミュニティの中で、お互いに助け合いながら生きているのが人間の本質だというわけです。共同体感覚とは、そんな社会の一員として「自分は必要とされている」「自分も役に立ちたい」という意識を持ち、他者とのつながりを積極的に感じられる状態を指します。
2-2. 「所属感」と「貢献感」
共同体感覚をもう少し噛み砕いて言えば、「自分はこの集団・社会に居場所がある」という所属感と、「その社会のために自分が役立っている」という貢献感の両方が満たされている状態です。誰かに受け入れられていると感じるだけでなく、「自分も何かしら貢献できている」と思えることで、相互尊重や連帯感が深まります。アドラーが言う「共同体」は、必ずしも大きな社会だけでなく、家庭や友人グループといった小さな単位を含む概念です。
3. 「自己受容」「他者信頼」「貢献感」という三要素
3-1. 自己受容 (Self-acceptance)
共同体感覚を育むためには、まず「自分自身をあるがままに受け入れる」ことが必要です。劣等感に苛まれたり、逆に虚勢を張って優越感に溺れたりすると、他者との健全な関わりを築きにくくなります。「自分は自分でいい」「不完全な自分でもここにいていい」と思える感覚が、共同体とのつながりを素直に受け入れる土台となるのです。
3-2. 他者信頼 (Confidence in others)
次に必要なのが「他者信頼」。他人を「敵」ではなく「仲間」と見なす姿勢を指します。ここでいう信頼は、「相手が必ず自分を裏切らない」という盲目的な確信ではありません。むしろ、「裏切られるリスクがゼロでなくても、それでも信じてみる」という選択的な態度を意味します。人間関係で傷つくことを恐れ続けると、結果として孤立を招きやすく、共同体感覚からは遠ざかってしまうのです。
3-3. 貢献感 (Sense of contribution)
最後は「貢献感」。共同体の中で「自分は役に立っている」と感じることが、自己肯定感と他者への感謝の気持ちを同時に育ててくれます。職場でも家庭でも、誰かに喜んでもらったり、問題解決に協力できた経験があると、それが次の意欲につながります。逆に、自分がどんなに努力しても誰の役にも立てないと感じると、共同体感覚は薄れてしまい、疎外感や無力感が強くなるでしょう。
4. 共同体感覚が欠如するとどうなる?
4-1. 孤立感と劣等感
共同体感覚が欠如すると、人は「誰ともわかり合えない」「自分の居場所がない」といった孤立感を強く抱きがちです。その結果、ますます他者との距離を取り、自分を守るために殻に閉じこもってしまうことがあります。また、「みんなから必要とされていない」と感じると劣等感が深まり、「どうせ自分なんて」と投げやりになるケースも考えられます。
4-2. 過度な競争や優越性の追求
一方で、共同体感覚が欠如している人の中には、過剰な優越性の追求に走る例もあります。「自分は孤立しているが、それでも他人に負けたくない」といった心理から、競争や攻撃的な態度で他者を蹴落とし、相対的な優位に立とうとするのです。これは、一見すると“強い人”のように見えますが、実は孤立を恐れるあまり、他者を排除しようとする守りの姿勢とも言えます。
4-3. 社会的問題行動
アドラー心理学の視点では、非行やいじめ、暴力などの社会的問題行動も、「共同体感覚の欠如」が大きな背景要因になっていると考えられます。仲間意識が希薄になり、「どうせ自分なんて誰からも必要とされていない」という想いが募ると、問題行動によって周囲の注目を引こうとする心理が働くことも少なくありません。
5. 共同体感覚を育む方法
5-1. 認知の転換:仲間視点の導入
共同体感覚を育むには、まず「他者や社会をどのように捉えているか?」という認知を見直すことが大切です。たとえば、他人を基本的に「自分を否定する相手」と感じているなら、そこを「自分とともに学び合う仲間かもしれない」という視点に少しずつ切り替えてみることが有効でしょう。完璧に信頼できなくても構いません。**「相手にも事情がある」「自分を責めたいわけではない」**など、ネガティブな決めつけを緩めるだけでも変化が生まれます。
5-2. 小さな貢献から始める
貢献感を育むためには、「完璧な貢献」を目指す必要はありません。たとえば職場であれば、小さな雑務を率先して手伝う、同僚が困っているときに声をかけるなど、誰にでもできる些細なサポートが第一歩になるでしょう。自分の日常生活でどんなふうに周囲を手助けできるのかを考え、実行してみる。そうした体験の積み重ねが、「自分はこの共同体に役立てる存在なのだ」という自己認識を育んでいきます。
5-3. 承認や感謝を言葉にする
共同体感覚を高めるもう一つの方法は、相手の存在や行動を「意識して言葉で承認・感謝する」ことです。人は誰しも、自分の存在や努力を認めてもらえると嬉しいものですし、承認や感謝を伝える側も「他者の存在価値」を実感しやすくなります。これによって、自他双方の“仲間意識”が強まりやすいというわけです。
6. 共同体感覚とライフスタイルの関係
6-1. ライフスタイルが共同体感覚を阻むことも
先に解説した「ライフスタイル」は、人間の思考・行動パターンを一貫して方向づける概念でした。もしライフスタイルの中核に「他人は競争相手である」「自分は常に評価されるべき存在」という信念がある場合、共同体感覚を持ちにくい傾向が強まります。これは、幼少期から染み付いた思い込みであり、本人の努力だけでは簡単に外せないこともあるでしょう。
6-2. ライフスタイルの書き換えによる共同体感覚の醸成
とはいえ、アドラー心理学が強調する「自己決定性(Creative Self)」に基づけば、ライフスタイルを変容させる可能性は常にあります。「自分は社会に貢献できる」「周囲の人々は仲間である」という新しい信念を少しずつ取り入れていけば、行動パターンも徐々に変わり、共同体感覚が強まっていくでしょう。これは、思考→行動→結果→再解釈というフィードバックを通じて進むプロセスで、日々の小さな成功体験の積み重ねが鍵を握ります。
7. まとめ
共同体感覚(Community Feeling)は、アドラー心理学の根幹ともいえる考え方であり、「自分は仲間の一員であり、互いに助け合うことができる」という肯定的な社会観を指し示します。これが確立されると、個人の精神的健康だけでなく、対人関係の質や社会全体の調和も高まっていく可能性が大いにあるのです。
- 共同体感覚の三要素
- 自己受容: ありのままの自分を認める。
- 他者信頼: 他人を敵ではなく仲間として見る。
- 貢献感: 社会や他者に役立っているという実感を得る。
共同体感覚が欠如すると、孤立や劣等感、あるいは過度の優越感などが生じ、対人関係のトラブルの原因になりやすいですが、逆に共同体感覚が育まれていると、互いを尊重し合い、協力し合う関係が自然と生まれます。これこそがアドラーが目指した「誰もが幸せを感じられる社会」の実現に向けた大切なステップと言えるでしょう。